Active Directory (AD) は、長らく企業のユーザー認証と端末管理の基盤として機能してきました。
社内LANに接続した Windows 端末とオンプレミスの業務アプリを守るには十分でした。
しかし、クラウド利用とリモートワークが一般化した今、ADの前提である「境界防御モデル」は限界を迎えています。
多くの企業が「脱オンプレAD」を掲げ、Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory) や IDaaS (Identity as a Service) への移行を検討するようになりました。
本稿では、実際に移行を進める際に立ちはだかる技術的な壁とその解決策に焦点を当てます。
「ADを一気に廃止したい」と考えても、現実にはファイルサーバーやプリンター認証などオンプレ資産が残ります。
こうした環境では Hybrid Microsoft Entra Join 構成やEntra ID をもとにしたSSO認証のソリューションの導入が現実的な選択肢です。
Microsoft Entra Connect を利用またはSSO認証を導入することで、ユーザーはクラウド・オンプレをまたいで同じアカウントを利用可能になります。
そのうえで、段階的に SaaS やクラウドアプリの認証を Entra ID に寄せていけば、最終的にオンプレADの役割を縮小・撤廃していくことが可能です。
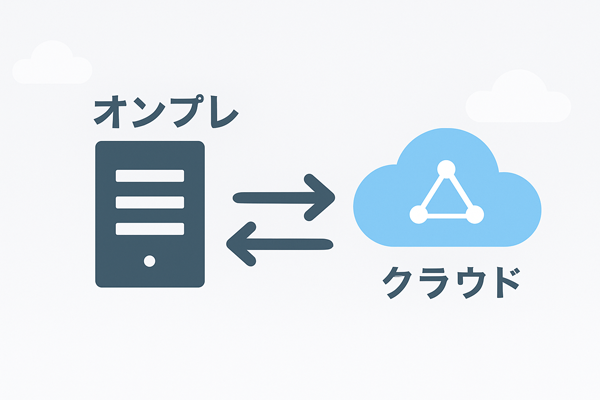
オンプレADの強みの一つはGPO (グループポリシーオブジェクト) による端末制御でした。
しかし、Microsoft Intune や MDM によるクラウドベースのポリシー管理に移行するにあたって、設定項目のギャップやGPOの洗い出しに行き詰まるケースもあります。
そんな場合には Intune のグループ ポリシー分析も有効です。
グループ ポリシー分析を使うことで、早期に Intune 上で再現可能な設定と個別に対応を進めていく必要がある設定を区分けすることができます。
個別に対応が必要な設定については構成プロファイルの作成や、コマンドやレジストリを Intune で配布できる PowerShell スクリプトやアプリといった形式に落とし込みによって実現可能なケースもあります。
また、Copilot を活用してポリシーやプロファイルの草案を作成したユースケースも報告されています。
オンプレADのモデルは「社内LAN=安全」という前提で設計されていました。
しかし、クラウド移行後は社外からのアクセスが前提となるため、VPNを経由する方式では通信帯域やユーザー体験に限界があります。
オンプレADから脱却し、ゼロトラストモデルを採用するには、「常に検証する」仕組みの導入が不可欠です。
具体的には、Entra ID の条件付きアクセスを活用し、アクセス元の端末状態、位置情報、リスク判定に応じて認証強度を動的に調整します。
さらに多要素認証 (MFA) を組み合わせることで、不正利用のリスクを低減します。
加えて、侵入を前提としたセキュリティー設計として、ネットワークを細かく分割するマイクロセグメンテーションを実施することで、攻撃が広がるのを防ぐことができます。
最後に、運用担当者のスキルセットの転換も大きな課題です。
オンプレADは「自社でサーバーを構築・管理する」発想でしたが、クラウドID基盤はサービスの設定・統合・運用設計が中心です。
監査ログ分析、権限委任モデルの設計、自動化ツールの活用といった新しい知識が求められます。
段階的なトレーニングやベンダー支援を取り入れ、運用体制そのものをクラウド前提にアップデートしていくことが必要です。
脱オンプレADは単なるコスト削減ではありません。
ゼロトラスト、クラウド利用、モバイル対応といった次世代の働き方を支える基盤強化です。
成功の鍵は「移行時の課題を正しく見極め」「段階的に解決策を実装すること」にあります。
ユーザー体験の改善とセキュリティー強化を同時に実現し、企業全体のDX推進を大きく後押しするためにも一つ一つ進めていくことが重要です。
当社では、こうした取り組みに貢献するソリューションとして、管理者が承認したアプリケーションのみをユーザー自身で安全にインストールできる "アプリケーション配布管理ツール" の「AppSelf」や、PCのデータレス化によって情報漏えいリスクを軽減するデータレスクライアントの元祖、"データレスPCソリューション" の「Passage Drive」をご提供しています。
ゼロトラスト時代のセキュリティーとPC管理の運用効率を両立することで、脱オンプレAD後の運用負荷を軽減し、情シスの働き方改革にも貢献します。

加藤 祥輝 (横河レンタ・リース株式会社 ITソリューション事業本部 ソフトウェア&サービス部)
自社ソフトウエアのカスタマーサクセスを担当。
現場の声を活かした提案や、サービスの改善に取り組みながら、社内外への情報発信も行っている。