最近よく聞く「ESG」をご存じですか?
作成日:2022/08/19
更新日:2025/05/16
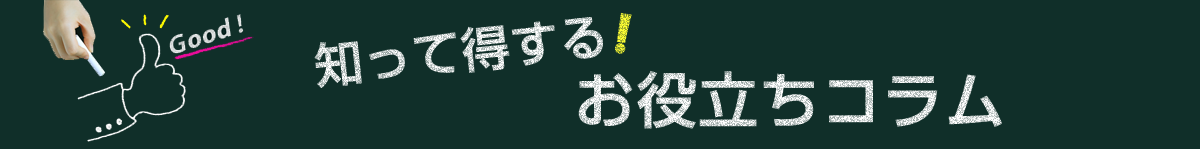
最近よく聞く「ESG」をご存じですか?
今回は、「SDGs」と共によく聞かれるようになった「ESG」についてご紹介します。
「ESG」、「ESG投資」って最近よく聞きませんか?
「SDGs」という言葉がメディア等で頻出していますが、同様に「ESG」、「ESG投資」という言葉に触れる機会も多くなってきたのではないでしょうか。
ただし、「SDGs」は国、企業や個人まで地球上のすべての人が協力して取り組む目標であることに対して、「ESG」は企業のコーポレイトサイトや経済ニュースを中心に企業や投資にまつわる内容で取り上げられるため、「SDGs」という言葉ほど普及していないような気がします。
ちなみに、筆者はコロナ禍で少額投資を始めたこともあり、証券会社のメールで初めてこの言葉を見かけた気がします。
「なんとなく」で投資を始めていますので、残念ながら初見の際は「投資専門用語か?難しそうだからいいや」と興味を持たず、たびたび単語は目にするため、知った気になって最近まで過ごしてきました。
「ESG投資」はなぜ注目されているのでしょうか?
「ESG」は環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Governance) 頭文字三つを取った造語で、「ESG投資」は投資先の企業を評価する際に財務情報だけではなく、財務情報に表現されない (非財務情報と言います) これら3要素に注目し、企業がどの程度それらの課題に取り組んでいるかを考慮して投資を行うことを指します。
ESG の課題の例
| 環境 (Environment) | 気候変動、資源の枯渇、廃棄物、汚染など |
|---|---|
| 社会 (Social) | 人権、従業員の労働・安全・衛生管理など |
| ガバナンス (Governance) | コンプライアンス、情報開示など |
ESG という言葉は国連が2006年に機関投資家に対し、ESG を投資プロセスに組み入れる「責任投資原則 (PRI (Principles for Responsible Investment)」を提唱したことをきっかけに広まりました。
日本では、年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) が2015年に署名したことを受け、広まり、重要視されるようになってきました。
PRI 6つの原則
| 1. | 私たちは、投資分析と意思決定のプロセスに ESG の課題を組み込みます |
|---|---|
| 2. | 私たちは、活動的な所有者となり所有方針と所有習慣に ESG の課題を組み入れます |
| 3. | 私たちは、投資対象の主体に対して ESG の課題について適切な開示を求めます |
| 4. | 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ実行に移されるように働きかけを行います |
| 5. | 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために協働します |
| 6. | 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗 (しんちょく) 状況に関して報告します |
出典:国連グローバル・コンパクト PRI:責任投資原則
つまり、PRI は署名機関に対して、投資活動の際には ESG を考慮し、投資対象には ESG 関連の情報開示を求め、署名機関同士でも交流し、自身の活動状況の情報開示やPRI普及に努めることを求めています。
従来、取引先や機関投資家、金融機関が企業の価値を評価する際に財務諸表ベースの指標を参考にしてきました。
そのため、対象の企業が売り上げや利益を上げるために、環境破壊や違法労働などを行っていても財務諸表からは読み取れないため、投資判断に考慮しにくい状況でした。
しかし、昨今では、例えば、目先の利益にとらわれ、環境破壊につながる行為をしていたことが発覚した企業の商品はメディアやSNSでバッシングを受けたり、企業自体も取引先から取引を停止されたりと社会的制裁を受け、企業価値を損なう可能性があります。
また、消費者が不買運動を行うことで業績が落ち、環境に配慮しない行動は企業の成長を阻害する要因になる可能性もあります。
これまで、多くの投資家は「環境や社会を意識した投資はリターンが小さい」と考えられていましたが、近年では、「環境や社会を意識した投資はリターンが大きくリスクが小さい」という研究結果も多く発表されています。
気候変動や世界的な労働環境の変化など、社会問題と向き合い貢献し、共に成長するといった姿勢を含めて企業の長期的な持続可能性を評価して投資する必要性が認識されてきています。
企業側が ESG の課題に取り組むことは、経営リスクの軽減や企業・価値イメージの向上、財源の確保などさまざまなメリットがあります。
PRI は投資家に対して ESG を考慮する行動を求めていますが、お金の受け取り側である企業の行動も、結果的に変化することを期待されています。
このような流れのなかで、ESG に取り組む会社の企業価値はあがり、ESG に無関心な企業は相対的に企業価値が下がる可能性もあると言われています。
そのため、積極的に ESG の課題に取り組む企業が増えています。

ESG の課題にITがどのように関わるか
企業が ESG の課題に取り組む場合、情報システム部門としてどのような対応ができるものでしょうか。
例えば、既に当たり前になっていますが、サーバーを電源効率の良い製品に置き換えることやサーバーを統合することで稼働効率を上げて、サーバーの稼働時の消費電力によるCO2削減に取り組むことが挙げられます。
2021年にはサーバー自体を自社で持たず、クラウドサービスを利用することでCO2削減に貢献できるというレポートが発表されました。
サーバーのエネルギー効率は機器が新しいほど良いという根拠が元になります。
クラウド事業者は積極的に新しい機器を採用し、データセンター施設も一般的なデータセンターと比較して冷却設備や電源環境が新しく効率の良い環境を利用しています。
そのため、クラウド事業者はサーバーやデータセンター設備をオンプレミス環境と比較して短期間でリプレースしている傾向にあります。
一見、短期間で更新していくことは経営を圧迫してかえって良くないと思われますが、クラウド事業者はサーバーの運用効率や電力消費量削減が経営効率に大きく影響するため、積極的に設備更新をすることで、電力・CO2を削減し、処理性能も高めることで、経営効率を上げられる構造になっています。
レポートはアジア太平洋地域全体を対象にした調査で、特に日本はITシステムのエネルギー効率がアジア太平洋地域全体の平均より低いという結果でした。
理由として挙げられるのは、サーバーのライフサイクルが長く、新しいサーバー・プラットホームの導入が遅れていること、仮想化率も他国と比べて低いためと言われています。
しかし、この欠点をデータセンター側の設備の効率的な運用で相殺し、ITインフラ全体のエネルギー効率はアジア太平洋地域の平均より高い結果になっていると報告しています。
このレポートを受けて、ESG への関心の高まりとともにより一層クラウド移行が注目されているのではないでしょうか。

他にも、ITベンダーや業務委託先などに、調達から開発、運用、廃棄などあらゆるフェーズにおいて、ESG に配慮した活動を行っているか、行うように求めることも必要になってきます。
これまでの情報システム部門は経営層やエンドユーザーが求めるITサービスを提供することが基本的なミッションでしたが、ESG の課題への積極的な取り組みが求められると言われています。
まとめ
今回は、ESG を中心にIT部門がどのようなかかわりを持つかを含めてまとめてみました。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
執筆
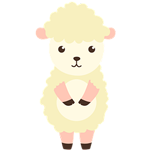
文月 (横河レンタ・リース株式会社 営業統括本部 ITS&システム営業推進本部 システム営業技術支援部1グループ)
主な業務は営業に対する技術支援やお客さまや社外向けプロモーション活動。
寺社仏閣めぐり (もちろん御朱印集めも) など日本の文化が大好きです!




