DX実現を阻む「レガシーシステム」が引き起こす問題とその解決策
PC管理
IT基礎知識
セキュリティー対策
- 公開:
- 2025/02/14
さまざまな企業がDX推進に力を入れるなかで、大きな障壁となっているのがレガシーシステムの存在。
レガシーシステムとは、導入されて長い歳月が経過したシステムのことを指します。
経済産業省によれば、レガシーシステムが刷新されない場合、2025年以降に年間最大12兆円もの経済損失をもたらすとの試算を発表しています。
レガシーシステムが引き起こす問題と解決策について解説します。
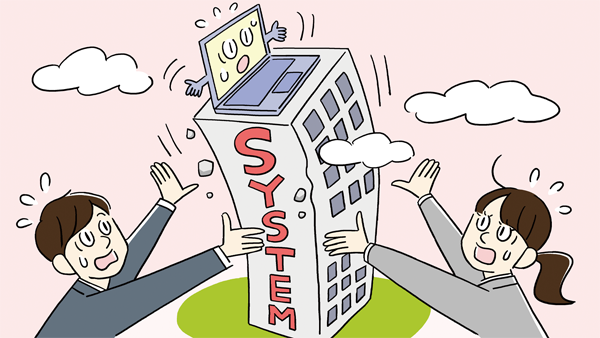
レガシーシステムとは?
レガシーシステムとは、「企業が長期間にわたり利用している老朽化したシステム」のこと。
導入当初の目的には適していたものの、技術の進化やビジネス環境の変化によって、現在のニーズや要件に対応できない状況になってしまっているシステムや、長期にわたって利用・改修されたことで古く、かつ複雑になったシステムなどが、レガシーシステムの代表的な例です。
「古く、維持管理しにくい」レガシーシステムの特徴
レガシーシステムの特徴は大きく以下の3つが挙げられます。
レガシーシステムの特徴1. 古い技術を使っている
レガシーシステムでは、古い開発言語、オフコン (オフィスコンピューター) やメインフレームといった旧世代のハードウエア、古いバージョンのデータベースやアプリケーションなどが使用されています。
新しいシステムとの互換性が低いうえに、万が一故障やエラーが発生したとしても、サポートが終了していたり、対応できる人材がいなかったりする場合があり、その結果としてシステム障害のリスクが高くなります。
レガシーシステムの特徴2. マネジメント性が低い
長期的に利用しているシステムは、機能拡張を繰り返すことで複雑化・肥大化していき、マネジメントが困難になるケースが多々あります。
また、近年はサイバーセキュリティーの脅威も増大しており、今後も同じシステムを使い続けるのであれば、今まで以上に維持管理における業務は高度化・複雑化していくでしょう。
レガシーシステムの特徴3. ブラックボックス化している
レガシーシステムでは、「秘伝のタレ」的に継ぎ足しで機能実装や変更が加えられた結果、誰も全体のシステム構成を把握できない状態が起こります。
システム開発や運用などの業務の多くはドキュメントで整備されておらず属人化、導入当初から関わっている社内のベテランエンジニアが引退するとともに、システムがブラックボックス化してしまうケースは少なくありません。
レガシーシステムが、コスト増や属人化につながる
2018年に経済産業省が行った調査によると、およそ80%の企業が「レガシーシステム」にあたる社内システムを抱えているとされています。
具体的に、レガシーシステムを使い続けるとどのような問題やリスクが発生するのでしょうか。
保守・運用のコストやリソースが増える
設計や開発から長期間経過しているため、新しいシステムと比較すると運用効率が低下しており、維持管理には多大な費用とリソースを必要とします。
多くの企業では複雑化したレガシーシステムの保守に人的リソースや予算が割り振られており、新しい技術やシステムへの投資を妨げる要因の1つにもなっています。
業務の属人化・サイロ化が進む
レガシーな技術やシステムに対応できる技術者が数少なく、必然的に数名のベテランエンジニアに業務が集中してしまいます。
こうなってしまうと、システム全体を俯瞰 (ふかん) して管理できる人がいなくなるだけでなく、万が一担当者が離職した場合、システムは完全にブラックボックス化。
大規模な改修は困難を窮めます。
システム障害のリスクが高まる
レガシーシステムは、何度もつぎはぎに改修を重ねることでコードや設計が複雑化しているケースが多くみられます。
新しい技術との連携で不具合が生じる、またシステム障害時にも原因究明に時間がかかる、さらにはサイバー攻撃やウイルス感染といった脅威にさらされ、最悪の場合は機密情報の流出やサービス停止といった事態に陥ってしまうことも考えられます。
最適化とシステム移行で、レガシーシステムから脱却したい
DX推進のためには、レガシーシステムからの脱却が必要不可欠です。
そのためには、どのような対策や方法が有効になるのでしょうか?
業務プロセスの整理と最適化
レガシーシステムからの脱却は、ビジネスモデルの変革や事業成長などを目的として行われるものであり、システムの刷新が目的化してはいけません。
現状を分析せずに、最新のシステムにリプレースしてしまうと、業務に支障をきたして現場から大きな反発を受けることになるでしょう。
開発部門だけでなく、事業部門や経営層などと密に連携しながら、業務の取捨選択や整理を行ったうえで、新しいシステムへの移行・構築を行うことが肝心です。
段階的なシステム移行
先に述べたように、抜本的で性急なシステムの改革は現場からの反発を招きます。
特に、大規模なレガシーシステムの場合は、機能や部門単位でサービスを分割し、段階的にモダンアーキテクチャへと移行させていくことが必要でしょう。
具体的な手法としては、モダナイゼーションやマイグレーションなどが挙げられます。
モダナイゼーション (Modernization)
モダナイゼーションとは、レガシーシステムのデータやプログラムを生かしつつ、モダンな技術やビジネス要件に適応させるプロセスを指します。
このアプローチは、既存システムの運用効率を向上させ、セキュリティーを強化しつつ、新しいテクノロジーを統合することを目的としています。
マイグレーション (migration)
マイグレーションは、もともと英語で移住・移転・移動などを意味する言葉で、IT用語では既存のシステムやデータを別の環境へ移行するプロセスを指します。
既存のシステムに手を加えることなくシステムの刷新ができるため、モダナイゼーションと比べると業務プロセスを大きく変えることなく、かつコストも比較的抑えられます。
しかし、根本的な解決につながらない恐れもあるため、注意が必要です。
ITに精通した人材の採用・育成
レガシーシステムの脱却では、技術的な側面だけでなくベンダーとの関係性や社内体制の見直しなど、組織的な側面も非常に重要です。
特に、過度にベンダー依存している場合、バージョンアップデートや新機能の実装といった細かい変更にも時間を要してしまいます。
システムに関する技術や知識が社内にプールされるように、ITに精通した人材の採用や育成を行って開発を内製化することが肝要といえるでしょう。

管理部門主導で、レガシーシステムから脱却を
単に「新しいシステムを導入する」のような目標では、DXそのものが目的化となってしまい、レガシーシステムからの脱却は果たせません。
かといって、現場の声に耳を傾けすぎると、理想からかけ離れたシステムになってしまいます。
システム移行のロードマップや全体像などは、開発部門や情報システム部門、経営層などが意思決定をしてグリップしつつも、現場の意見を吸い上げてそれを可能な限り反映させていくバランスが極めて重要といえるでしょう。








