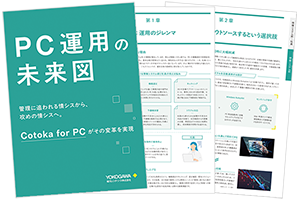ヘルプデスクがストレスを抱える原因や軽減する方法を紹介
PC管理
- 公開:
- 2025/03/21
- 更新:
- 2025/12/01
ヘルプデスクでは、主に従業員や顧客からの問い合わせやクレーム対応を行います。
しかし、中には業務範囲外の問い合わせや理不尽なクレームが届いたり、少人数で対応しなければならなかったりすることから、心身ともに疲弊し、ストレスを抱えるケースもあります。
そのため、ヘルプデスクのストレスをなるべく軽減するには、業務量や業務範囲を見直したり、業務効率化に役立つ仕組みを整えたりすることが大切です。
この記事では、ヘルプデスクがストレスを抱える主な原因と、その負担を軽減する方法をご紹介します。

当社では、機器調達やPC運用管理時に発生する手間や課題を解消するサービスを展開しています。
以下リンクから、当社が提供するPC関連サービスをご覧いただけます。
ヘルプデスクはストレスを抱えやすい?
ヘルプデスクとは、社内の従業員や顧客からのITに関する問い合わせに対応する部門や業務のことを指し、従業員からの問い合わせに対応する社内ヘルプデスク、顧客からの問い合わせに対応する社外ヘルプデスクの2種類に大きく分けられます。
社外ヘルプデスクでは、主に自社が提供するIT製品の使い方や不具合・トラブルに関する問い合わせ、顧客からのクレーム対応を行います。
社内ヘルプデスクにおいても、社内で使用するPCなどのIT機器・ソフトウエアの使い方や、不具合などの問い合わせ対応を行い、従業員がスムーズに業務を進められるようサポートするのが主な業務内容です。
社外ヘルプデスクでは、上記のような問い合わせ・クレーム対応を主に電話やメールで行います。
一方で、社内ヘルプデスクでは問い合わせ対応以外にも、不具合が発生している現場に赴いて機器の状態を調べたり、メンテナンスを行ったりすることもあるため、業務内容が多岐にわたり、専門的な知識やスキルが求められることもあるでしょう。
このように、ヘルプデスクでは問い合わせやクレーム対応をこなしたり、業務内容が多岐にわたることで業務負担が大きくなりやすかったりすることから、ストレスを抱えやすい仕事であるといわれることもあります。
ヘルプデスクと社内SEの違い
ヘルプデスクと似た職種に社内SEがあります。
社内SEは自社のITに関するシステムの導入や運用などを行い、ヘルプデスクよりも専門的な知識やスキルが必要です。
社内SEでは、企業の経営戦略などを理解した上で、事業を円滑に進められるよう適切なITシステムを考案し、上層部への提案や導入、開発、運用、保守といった一連の管理業務を行うため、社内SEの導入したITシステムが社内全体の業務効率にも影響するとも考えられるでしょう。
なお、企業によっては社内SEがヘルプデスクの業務を担っていることもあるため、ヘルプデスクと社内SEが同じ職種であると混同されるケースもあります。
しかし、一般的にヘルプデスクでは、主に従業員や顧客からの問い合わせ対応を中心に行い、社内SEでは、社内へのITシステムの導入や管理、開発、保守などをメインの業務としているため、ヘルプデスクの専門部署が設けられている場合は、ヘルプデスクではITシステムの開発や運用などは行いません。
ヘルプデスクがストレスを抱える主な原因

上記では、ヘルプデスクの主な仕事内容や社内SEとの違いについてご紹介しました。
上記でも触れたように、ヘルプデスクでは従業員や顧客からの問い合わせ・クレーム対応などによって業務負担がかかりやすいことから、ストレスを抱えやすい職種といわれる場合もあります。
ここでは、ヘルプデスクがストレスを抱える主な原因について詳しくご紹介します。
業務範囲外の対応を任されることがある
ヘルプデスクでは主に問い合わせ対応を行いますが、「PCのセットアップを行ってほしい」など業務範囲外の対応を任されることもあります。
業務範囲が広くそれぞれの対応内容に関する専門知識を持っていなければスムーズにタスクを処理できず、ストレスを抱えることもあるでしょう。
また、社内で社内SEや総務部など他部署との線引きがあいまいになっている場合、本来はそれらの部署が対応すべき内容にもヘルプデスクが対応することとなり、さらに不満が募る可能性もあります。
人手が足りず属人化しやすい
ヘルプデスクを社内SEや情シス (情報システム部門) など他部署の担当者が兼任している場合、本来のコア業務とあわせて問い合わせ対応を行う必要があります。
しかし、これらの部署は売り上げや利益を上げないため、上層部から新入社員の採用コストをかけてもらえないことがあります。
そのため、常に人手が足りず業務過多となりストレスがたまるケースもあるでしょう。
また、少人数で業務をこなしている場合、特定の分野に関して知識のある担当者に対応業務が集中しやすく、属人化が生じやすいです。
そうした結果、担当者の休職や退職時の引き継ぎが難しかったり、後任の担当者が円滑に業務を進められなかったりする恐れがあります。
リソース不足に陥りやすい
上記のように、業務範囲外の対応や少人数での対応が慢性化していた場合、担当者一人ひとりがリソース不足に陥りやすく、常に業務過多な状態が続く恐れがあります。
一つの問い合わせ対応に時間がかかってしまった場合、そのほかの問い合わせ対応を業務時間内に処理できず、残業や休日出勤が発生することもあるでしょう。
一人当たりの業務量が多く、残業時間も増え続けている場合、担当者がストレスによって心身ともに疲弊し、休職や退職につながる恐れもあります。
トラブルの発生タイミングが読めない
ヘルプデスクではトラブルの発生タイミングが読めないため、常に緊張感を持ちながら業務に取り組む必要があります。
自身でスケジュールを組んで業務を進めることができないため、余裕を持って業務をできずにストレスがたまる場合もあるでしょう。
また、軽度なトラブルだけではなく、対応に時間がかかるトラブルや緊急性を要するトラブル、予想を超える大きなトラブルなどさまざまなトラブルが急に発生することがあるため、このようなトラブルの発生タイミングが読めない点もストレスになりやすいです。
リモートワークなどの多様な働き方が難しい
社内・社外を問わず、ヘルプデスクでは従業員や顧客の個人情報を扱うため、セキュリティーを維持するためオフィスで作業をしなければならないのが一般的です。
また、特に社内ヘルプデスクの場合は、社内のITシステムやPCなどに異常が生じた場合、現場に赴いて本体を実際に操作しながら対処する必要もあるため、セキュリティーの課題をクリアしたとしてもリモートワークが難しいのが現状といえます。
また、上記のようにいつトラブルが発生するか読めないため、フレックスタイム制を利用しての勤務や時短勤務などの働き方も難しいでしょう。
そのため、企業ではリモートワークやフレックスタイム制を導入していたとしても、ヘルプデスクでは利用できず定時で出社勤務しなければならないため、ほかの従業員との働き方の差にストレスを感じることもあるでしょう。
繁忙期と閑散期の差が激しいことがある
ヘルプデスクにも繁忙期があり、例えば決算期や新入社員の入社タイミングなどは多くの不具合やトラブルが発生しやすいです。
そのため、大きなトラブルの処理に追われ、基本的なPCの操作方法などの初歩的な内容に関する問い合わせが後回しになってしまい、従業員の業務スピードが落ちてしまうといった課題が生じることもあるでしょう。
一方で、閑散期で問い合わせがあまり届かない時期にはやることがなく、時間を持て余してしまう可能性があります。
ヘルプデスクを社内SEや情シスが兼任している場合は、それらの業務にリソースを集中させられますが、ヘルプデスク専任である場合は、ほかの対応業務がないためモチベーションが下がる恐れがあります。
理不尽なクレームにも対応しなければならない
社外ヘルプデスクでは、まれに顧客の使用している通信回線や機器に問題があり不具合が生じているにもかかわらず、自社の製品に問題があるのではないかとクレームを送るなど、理不尽なクレームを受けることもあります。
そのような場面においても、ヘルプデスクは冷静に顧客に向き合う必要があるため、人によっては反論できないもどかしさにストレスを感じることもあります。
また、顧客がITに関する知識やスキルが乏しい場合、相手に伝わるように説明しなければなりません。
説明に対して相手からの理解が得られなかった場合、さらにクレームが続く可能性があるため、わかりやすく丁寧な説明を根気強く続けることが求められます。
このようなクレームへの真摯な対応は精神的にも負担がかかりやすいため、強いストレスを感じる人も少なくないでしょう。
高いコミュニケーション能力が求められる
問い合わせ対応では、上記のようにITに関する知識やスキルを持たない人に説明することも多いです。
そのため、このような従業員や顧客にも理解してもらえるよう、相手の話からトラブルの内容を正確に読み取り、適切な解決策をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力の高さが求められます。
特に、問い合わせ対応は電話やメール、チャットなど相手の顔が見えない状態で行うため、少ない情報量でいかにわかりやすく伝えられるかが重要です。
また、トラブルの内容によっては、他部署に対応を依頼したり、経営陣に相談したりする必要があるものもあります。
ほかの部署ともスムーズに連携を取ったり、経営陣からの理解を得やすくするために働きかけたりする際にも、高いコミュニケーション能力が必要となるでしょう。
ヘルプデスクだけで対処できないトラブルがある
トラブルの内容によっては、ヘルプデスクだけでは対応できず、他部署やメーカーなどに対応を依頼するケースもあり、解決に時間がかかる場合があります。
このとき、ヘルプデスクでできることがない場合、ただ解決を待つよう伝えるしかないため、もどかしさを感じるでしょう。
また、このようなトラブルが続く場合、「ヘルプデスクがあるのに問い合わせても何も解決できない」とクレームにつながり、さらにストレスを抱えてしまうケースもあります。
なお、ここまでご紹介したように、ヘルプデスクは社内SEや情シスが兼任することもあります。
本サイトでは、情シスが抱える主な課題や解決策などをご紹介している記事や、情シスの「あるある」をご紹介している記事もあるため、ぜひあわせてご覧ください。
ヘルプデスクのストレスを軽減する方法

ここまで、ヘルプデスクがストレスを抱える主な原因をご紹介しました。
上記のような原因によって生じるストレスを軽減するためには、ヘルプデスクの業務量や対応にかかる負担を減らせるよう、簡単な問い合わせに自動で対応できる仕組みを整えたり、ヘルプデスク業務をアウトソーシングしたりするのがおすすめです。
ヘルプデスクのストレスを軽減する方法について詳しくは、次のとおりです。
業務量や業務範囲を見直す
ヘルプデスク業務が多く、残業が慢性化しているといった状態の場合は、担当者一人当たりの業務量が多すぎる可能性があるため、業務量や業務範囲を見直しましょう。
人手が足りないことや属人化が進んでいること、本来は他部署がやるべき対応をヘルプデスクが行っていることなど、現状を明確にすることで業務量や業務範囲が調整され、負担を軽減できる可能性があります。
なお、上層部に相談する際は、ネガティブな内容ばかりを伝えるのではなく、「私は〇〇の対応が得意でより迅速にこなせる自信があるため、△△の対応は専門的な知識を持っている××部門にお願いしたい」などポジティブな提案も含めることで、要望が通りやすくなるでしょう。
気軽に相談できる環境を用意する
「今は〇〇の対応に追われている」「〇〇の対応が来るとほかの対応に遅れが出てしまうことが多い」「最近は残業が続いている」などを定期的に上司との面談で話したり、カウンセラーや産業医に相談したりするといったように、現在のタスク状況や課題、悩みを気軽に共有・相談できる環境を整えるのもおすすめです。
ヘルプデスクは社内SEなどと兼任したり、少人数化しやすかったりする傾向があるため、周りに相談できる人がいない場合、一人で悩みやストレスを抱えてしまいます。
上記のように、上司やカウンセラーなどに気軽に相談できることで、ストレスを一人で抱え込まず、精神的な負担を減らせるでしょう。
FAQやチャットボットを作成する
従業員や顧客からよく届く問い合わせ内容をFAQやチャットボットにまとめることで、ヘルプデスクに問い合わせる前に従業員や顧客自身がFAQで解決策を検索したり、チャットボットが自動で解決策を提示できたりするため、問い合わせ数を減らせます。
従業員や顧客側で解決できる簡単な内容の問い合わせが多い場合は、このようにFAQやチャットボットを活用することで、ヘルプデスクの負担を軽減できるでしょう。
なお、上記のようなFAQやチャットボットの作成以外にも、本サイトでは情シス業務を効率化する方法についてご紹介している記事もあります。
ヘルプデスク業務を情シスで兼任している場合は、ぜひ参考にしてください。
問い合わせ管理システムを導入する
問い合わせ管理システムとは、社内に届く問い合わせを一元管理できるシステムのことで、各問い合わせの対応状況をまとめて確認できるため、対応漏れを防いだり、優先度を判断しやすかったりするなどのメリットがあります。
電話やメール、問い合わせフォーム、SNSなどさまざまなチャネルからの問い合わせを受け付けている場合は、問い合わせ数が増えることで対応漏れなどのミスも生じやすくなるため、このような問い合わせ管理システムを導入することで、効率よくヘルプデスクの業務を進められるでしょう。
なお、当社では法人向けのPC調達・運用サポートを行うサービスである「Cotoka for PC」を提供しています。
Cotoka の利用により、独自開発したプラットフォームである Cotoka Platform や Windows Autopilot を活用してPCの調達やセットアップにかかる負担を減らせるだけでなく、PC管理者やエンドユーザーを問わず、PCに関連する内容をはじめとしたさまざまな問い合わせに対応可能なヘルプデスクを設けています。
問い合わせ対応が追いつかない・リソースを圧迫しているといった場合は、ぜひ Cotoka の導入もご検討ください。
ヘルプデスク業務をアウトソーシングする
ヘルプデスクの人手が足りない場合や、一人当たりの業務量を軽減したい場合は、ヘルプデスク業務をアウトソーシングするのもおすすめです。
社内SEや情シスなどほかの業務とヘルプデスクを兼任している場合は、ヘルプデスク業務をアウトソーシングすることで、コア業務にも注力しやすくなるでしょう。
下記の記事も合わせてご確認ください。
情シス業務はアウトソーシングすべき?依頼できる内容や注意点を紹介
まとめ
この記事では、ヘルプデスクがストレスを抱える主な原因や軽減させるための方法をご紹介しました。
ヘルプデスクでは、業務範囲外の問い合わせ対応をしなければならなかったり、トラブル発生のタイミングが読めなかったりすることから、ストレスを抱えることも多いです。
また、社内SEや情シスがヘルプデスクを兼任している場合は、業務リソースを圧迫しやすく、常に一人当たりの業務負担が大きくなったり、コア業務まで手が回らなかったりする恐れもあるでしょう。
ヘルプデスクのストレスを軽減するためには、業務内容の見直しや気軽に相談できる窓口の設置など、ストレスなく働ける環境を整えるだけでなく、FAQなどの作成や問い合わせ管理システムの導入など、業務効率化が期待できる仕組みを作るのもおすすめです。
当社の「Cotoka for PC」は、デバイスの調達から Windows Autopilot を活用したキッティング、さらに運用中のヘルプデスク対応までをワンストップで提供するサービスです。
社内ヘルプデスクの人手不足解消や、情シス担当者の業務負担軽減を図りたい企業に最適です。
資料ダウンロード
「攻めの情シスを実現するPC運用とは?」
IT人材不足が深刻化する中、アウトソーシングが注目を集めています。
PC運用の未来図について、下記でご確認いただけます。